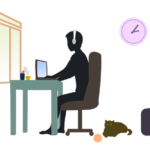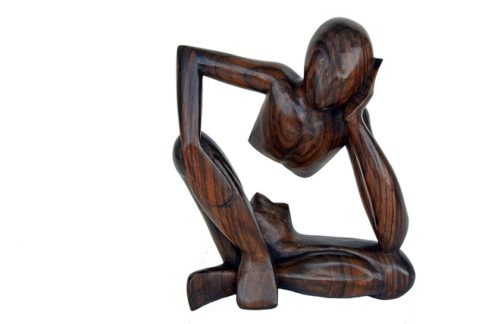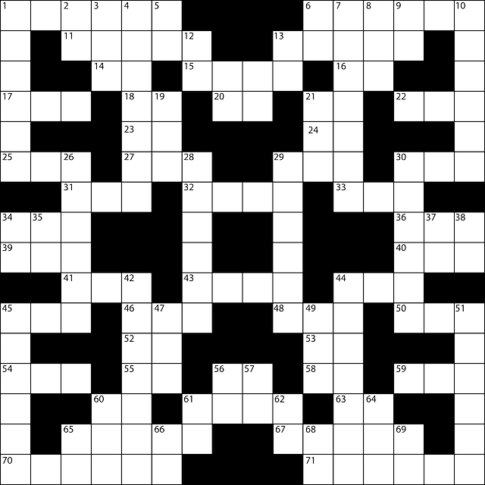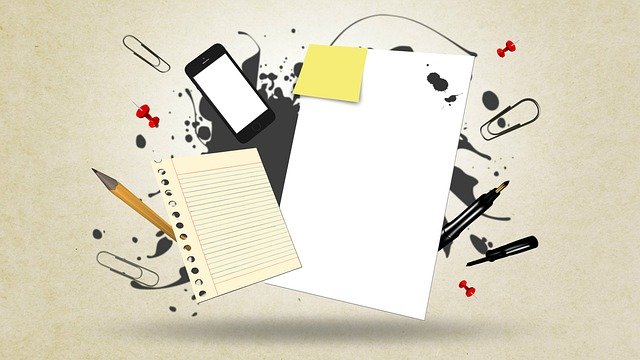
「考える」とはどういうことでしょうか?
たぶん、考えているだけでは「考えている」とは言えないと思います(なんのこっちゃ)。
知的生産その3「頭をはたらかせる」〜一個人の、知的生産・タスク管理の技術13〜
メモしたはいいが、なんだかよくわかってないような気がするもの。
全容が見えずモヤモヤするので、ちょっと立ち止まって考えてみて、よりはっきりとつかみたいもの。
わかっているようでわかっていなさそうなもの。
考えてみたら何か出てきそうで、まだまだ発展させていけそうなもの。
かなり自分の興味をひいてくるもの。
そういうものについては、ただ置いておくのではなく、自分からそれをメモしたものに働きかけて、把握したり膨らませたりするのがいいかな、と思います。
ざっくり言うと、「考える」わけです。
そのときにぼくは、まっさらな一枚の紙を使っていました。A4用紙の裏紙を取り出し、思いついたことを書き出していく。そうすると、全容がつかめずモヤモヤしていたものの輪郭や流れを掴むことができたり、より理解できたり、新たな発見があったり。
そしてこれこそが、知的生産という行為の中でもっとも大切なことではないか、と思ったりします。
考え、整理すること。
考え、理解すること。
考え、発見すること。
そこを経る、「頭をはたらかせる」からこそ、「なにかあたらしいことがら」をつかむことができるのでしょうし、「ひとにわかるかたちに」するためにまず自分自身が理解することができる。
そのあと「提出する」かは、実際はどうだっていいのではないか、とさえ思います。
引用した記事にある、
「考え、xxxすること。」
というxxxまでできて、はじめて「考えている」という言えるでしょう。
つまり何らかのアウトプットが得られるという事です。
例えば、「整理すること」とあります。
何か企画を考えているとき、具体的な企画案が出なくても、何かを「整理」してそれをアウトプットできれば、「考えていた」事になるという訳です。
逆に言うと、何もアウトプットが出なかったら「考えていた」ではなく「悩んでいた」や「迷っていた」ということです。
そして悩んだり、迷ったりしないためには、ここに書かれている「書き出す」という行動がとても重要になってくるわけです。
注意するのは、最終アウトプットだけを書き出すわけではないということです。
最終アウトプットだけだと、何か「レポート作成」的な雰囲気になります。
そうではなくて、アウトプットを出すまでの「作業の段階」から書き出すことが重要です。
この「作業」から書き出すことによって、より速く最終アウトプットに到達することができます。