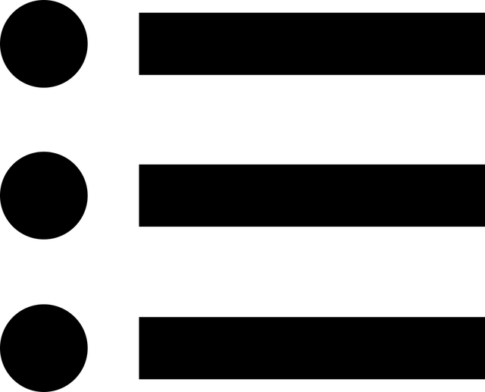何かの報告書を作成しなければいけないというシーンを想定してください。
自分では報告すべき内容は理解しているつもりなので、特に前準備をすることもなく、報告書を書き始めます。
よくあることですが、書いているうちに実は自分でも内容が整理されていないことに気づきます。
ただ、報告書が書けないわけではなく、書きながらだんだんと頭が整理されていくのを感じています。
整理されるので、筆が進んで資料が出来あがりました。
自分の頭は整理されていて自己完結しているので、「ふむふむ、なかなかよく書けた」などと思っている訳です。
誰が読む資料?
ところがこの文書は、他人が読んだ時に理解できないかもしれません。
それは、「自分の頭を整理しながら書いている」ことが原因です。
そういうときは、文書の中に「書いた本人だけが知っている情報」を前提にして説明している部分が残っていたりします。
なんでそうなるかというと、内容を整理しながら書いているうちに、「他人への説明資料」というよりも、「自分への説明資料」になってしまうからなんです。
自分の頭が納得するように書いているので、前提をあらかじめ知っている自分には、当然理解できる資料になっています。
ところが他人は前提が分かっていないので、説明の流れがつながりません。結果として納得できないわけです。
いかにも、おちいってしまいそうな罠です。
どうするか?
1. できれば他人にチェックしてもらう。
これが一番確実です。
自分ではない人が読んで、ちゃんと理解できるか?
できないなら、どの部分がそうなのかを教えてもらいます。
でも、そういう人がいないケースもあります。
2. 他人の観点で推敲する
そういうときには自分で「チェック」するしかありません。
チェックするときは「why so」を意識します。
「 それはなぜ?」
「その理由は、読む相手は知っていることか?」
これをくり返して不明な点がなくなるまで推敲します。
これをやれば、立派な説明資料ができます。
もう一つ、見方を変えると説明資料を書くことは、自分の頭を整理するのにとても有効な方法だということも分かりますね。
知識の整理と定着はアウトプットが一番です!