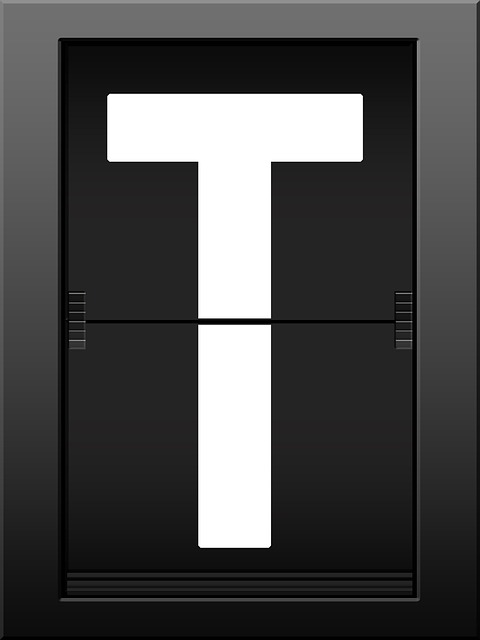何かを判断する時に、普通にネットで検索すると思います。
「検索」「判断」というと大げさですが、「どこでご飯食べよう?」とか「どこのホテルに泊まろう?」とかも、一つの検索と判断です。
今は、ネットでいくらでも情報を集められる時代なので、いくらでも調べられます。
検索の陥りやすい罠
普通に考えると、情報はたくさん集め方がよさそうに思えます。
私も、検索結果を何ページ分もクリックし、いろいろなページを読みふけったりします。
また、いろいろな検索ワードをとっかえひっかえして検索してみたりもします。
ほんと、「際限なく」できてしまうんですね。
例えば、Googleの検索結果はGoogleによってランク付けされています。
したがって、後ろの方に掲載されているページの情報は相対的に「劣る」はずです。
でも、
「いやいや、掘り出し物のデータがあるかもしれない」
と思い、続けてしまうんですね。
結局、情報の質が悪ので、時間をかける割にはいい情報が集まらない可能性が高いです。
多すぎる情報
さまざまな品質の情報が、「逆に」悪影響を及ぼすことも考えられます。例えば、
- 本来であれば悩まなくてもいい情報にとらわれて、間違った方向に進んでしまう。
- 選択肢が多すぎて、判断ができなくなる。
こう考えると、調べすぎるのは良くないことになります。
では、どうするか?インターネットでの調査を前提にして考えてみました。
何を調べるかを決めておく
「何のために」「何を」調べるかについて書き出して目に見えるところに置きます。紙でもPC、スマホでもいいです。
目的が見えなくなったり、目的と手段が逆転してしまうのは、調査の「あるある」です。
「何のために」「何を」を常に意識して必要な情報のみを読み込むようにします。
制限時間を決める
あらかじめ30分などと時間を区切っておきます。スマホのタイマーをかけておくのがいいでしょう。
時間が来たら、とりあえず調査をやめて、集めた情報の全体を俯瞰してみます。
最初に決めた「何のために」「何を」が網羅されていますか?
もし足らなければ 10分延長して、足らない部分にフォーカスして調べます。
一応、網羅されていればそこで調査をやめます。情報の量や品質に疑問を感じても、いったんやめて次のステップに進みます。
もし、後で情報が足りないとなったら、その時にまた調査をします。
情報を少し整理しながら調査する
セオリーから行くと、情報は集めた「後」に整理します。
でも、情報を際限なく集められる現代では、少し整理しながら集めた方がいいです。
さもないと、溜まってしまった大量の情報を整理する手間が大変になります。
そこで、情報を調べながら少し整理します。
集めた情報を、完璧でなくてもいいので、整理して見える化していきます。
情報の重複をチェックしながら進める訳ですね。
そうすれば、調査委を継続する必要性があるかどうかが分かりやすくなりますね。
目的と手段の逆転
検索の本来の目的は、情報を分析して判断することであり、集めることは手段に過ぎません。
でも実際には手段と目的が逆転しまい、集めることが目的となっていることがありませんか?
一度、ご自身の調査方法について振り返ってみるのもいいと思いますよ。